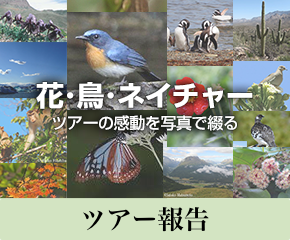【ツアー報告】出水・諫早・有明海 冬の九州縦断 2025年1月31日~2月2日

(写真:クロヅル 撮影:富川誠様)
冬の探鳥地といえば冬の道東が代表的ですが、冬の道東と並んで絶対に外せないのがこの九州でしょう。出水にはツルたちが集う世界的な越冬地があり、そこには全生息数の90%占めるナベヅル、50%を占めるマナヅルをはじめ、クロヅルやカナダヅル、そして年によってはソデグロヅルやアネハヅルが越冬しています。ほかにも世界的希少種のクロツラヘラサギやズグロカモメ、有明海の干潟にはさまざまなシギ類が群れ飛び、ツクシガモの大群も圧巻です。今回は鹿児島県の出水平野から諫早干拓、そして最後は有明海の干潟と九州を縦断しながら主に3カ所の代表的な探鳥地をめぐります。今回は春のような陽気からのスタートですが、1日は雨、そして最終日の現地は曇り予想ながら、関東地方では積雪の可能性があるとのことでした。
31日、この日の都内は早朝からすっきりした快晴。かなり混雑している羽田空港にご集合いただいた後は、この日の予定をお伝えしてから搭乗し、鹿児島空港に向かいました。ほぼ予定通り快晴の鹿児島空港に到着後は観察機材の準備をしていただいてから出発しました。この日はツルたちが群れる出水市に向かう予定でしたが、空港からわずかな距離にある場所に立ち寄りました。春のような暖かな陽気の中、堤防には11羽のクロツラヘラサギが群れて眠っていました。しばらく観察していると、寝ている個体も動きがありましたがすべてクロツラヘラサギのようでした。ほかにもカルガモ、マガモ、キンクロハジロ、コガモ、カイツブリ、さらにはタシギ、アオアシシギの姿もあり、観察中にはミサゴがとんできて魚を捕獲して電柱に止まりました。翌日が雨予報のため、少々早めに出発して、その後は休憩してから、いよいよ出水平野に向かいました。まずはツル観察センターに立ち寄って休憩を挟んでから周辺で探鳥してみました。ここではマナヅル、ナベヅルがかなりの数、見られ、水が張ってあるエリアにはツクシガモ、タゲリが見られました。またミヤマガラスの大群が右往左往していました。ただここで対岸の畑地にサカツラガンがいるとのことで行ってみると、ナベヅルの足元を歩き回っているサカツラガンの姿を見ることができました。その後は東干拓に向いましたが、幸運なことに途中の畑地にクロヅルがいたことからバスを降りて観察することができました。しばらく観察していると、付近にはミヤマガラスに混じる2羽のコクマルガラスの成鳥が見られ、電線にはホシムクドリが止まっていました。探鳥後に東干拓まで行くと、またまた幸運なことに間近に3羽のカナダヅルが歩いていて、こちらも間近に観察することができました。観察しているといつの間にか、かなり冷え込んできていて日中とは全く異なった体感気温になっていました。ここでも飛翔するマナヅル、ナベヅル、1羽で採食しているクロヅル、さらにはマガン、ツクシガモ、タシギなどが見られ、美しい夕陽を見ながらこの日の探鳥を終えました。
1日、この日は昨日の美しい夕陽からは想像もできないほど天気予報が芳しくなく、早朝に外に出ると雨は降っていなかったものの強風が吹き荒れていました。ひとまず早朝の塒から飛び立ってくるツルたちの姿を観察するために日の出前に出発しました。現地に到着するとまだまだ薄暗い中、ツルたちが続々と飛んでくる様子が見えました。外に出て観察をはじめると残念ながら日の出は見られなかったものの雨は降ってこず、続々と集まってくるマナヅル、ナベヅルの迫力に圧倒されました。またこの日も仲良く3羽で行動しているカナダヅルを間近に観察することができたほか、クロヅルも2個体見ることができました。観察後は一旦出発してホテルに戻り、朝食をいただいた後に再びツルたちを見に行きました。ただこの時間はかなりの雨が降っていたことからバスを使って観察をすることにし、前日同様のコースを回ってみました。すると前日にサカツラガンを見た場所とほぼ同じ場所にこの日もその姿があったことからしばらく車内から観察することができました。思いのほか観察が長引いたため、その後はトイレに立ち寄ってから熊本港フェリーターミナルに向いました。途中、各自昼食を準備していただき、その後は休憩、買い物をしていただき、ほぼ予定通りに熊本港フェリーターミナルに到着し、島原港に向けて出港しました。海上は雨は降っていましたが海況を悪くなく、餌を求めて飛んでくるユリカモメの群れを見ながら進み、堤防上にはウミウ、カツオドリが止まっていました。その後もユリカモメに混じって飛んでいる、ウミネコ、セグロカモメ、海上から飛び立つかなりの数のカンムリカイツブリが見られ、この日は飛んでいるカツオドリがかなりの数で見られました。島原に到着後は雨がやや激しくなる中、諫早干拓に到着しました。ただ、幸いなことに到着とほぼ同時に空が明るくなってきて雨はほぼ上がってくれました。駐車場で準備をしているとハイイロチュウヒのオスが飛び、堤防付近には2羽のチュウヒが飛んでいました。堤防に上がって広大なヨシ原を眺めると、枯れ木にはチュウヒが止まり、各所にハイイロチュウヒのメスの姿がありました。中には間近に飛んできてホバリングしながら餌を探す個体もいて、振り返ると2羽のハイイロチュウヒのオスが追いかけっこをするように飛び、地面にあるタイヤに止まって羽繕いをする姿まで見せてくれました。そして最後は美しいコチョウゲンボウのオスが枯れ木に止まって捕らえた獲物を食べる様子を観察してこの日の探鳥を終えました。終日ほぼ雨でしたが、探鳥した早朝と午後は雨に降られることなく終えられて幸いな1日でした。
2日、この日は終日曇り予報でしたが、朝食後に外に出ると早くも一部に青空が見えていました。川に行ってみると、かなり干潮の時間帯だったことから水位は低く、カルガモ、マガモ、ヒドリガモが見られ、浅瀬を数羽のタゲリが歩き回っていました。また2羽のズグロカモメがひらひらと飛び回って餌を探していました。ここでは昨年、ツリスガラが見られていたことから探してみましたが、なかなか見つからず、ホオジロやオオジュリン、アオジなどは見られました。ただ対岸のヨシ原の一部に数羽のツリスガラが飛んできて餌をとっていたことから、やや距離はあったもののその姿を見ることができました。その後は最後の探鳥地である東与賀の干潟に向かいました。ただこの辺りからはよくカササギが見られていることから外を見ていると、たまたま大きな照明に止まっている2羽が見られたため、バスを止めて車内から観察することができました。観察していると飛びたって、特徴的な長い尾も見ることができました。東与賀に到着後は各自準備をしていただいてから干潟に向いました。駐車場わきでは早くもズグロカモメが飛び、公園内にはジョウビタキの姿もありました。堤防上に立つとまだまだ潮が引いていることから無数のズグロカモメ、ツクシガモが群れ、干潟を歩き回るハマシギやシロチドリ、メダイチドリの姿がありました。この時点であと2時間ほどで満潮になることから干潟沿いに歩きながら探鳥してみました。ある場所ではアカアシシギが見られ、それ以降もアオアシシギ、オオハシシギ、ダイシャクシギなどが見られ、一番端までくるとツクシガモの混じる2羽のミヤコドリの姿もありました。来た道を戻るとかなり潮が上がってきていましたが、かなりの数のダイセンが群れ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、そしてハジロコチドリ、コオバシギも見られました。そして最後はダイシャクシギの群れに混じるソリハシセイタカシギ、ホウロクシギを見てこの日の探鳥を終えました。振り返るといつの間にか満潮になった干潟上をシギチドリが飛び回っていました。
今回は初夏のような陽気にはじまり、2日間はほぼ雨、そして3日目は雲が多かったものの雨はなく助かりました。出水では圧倒されるようなナベヅル、マナヅルの群れ、そしてカナダヅル、クロヅルを良い条件で見ることができ、ミヤマガラス、コクマルガラス、そしてサカツラガンに出会う幸運もありました。また諫早干拓ではトモエガモの大群は見られませんでしたが、ハイイロチュウヒのオス、メスの飛翔を堪能し、最後に訪れた東与賀では途中でカササギが見られ、干潟ではツクシガモ、ズグロカモメ、ハマシギ、ダイシャクシギ、ソリハシセイタカシギ、ミヤコドリ、ハジロコチドリ、ヘラサギ、クロツラヘラサギなどが見られました。この度はご参加いただきましてありがとうございました。
石田光史