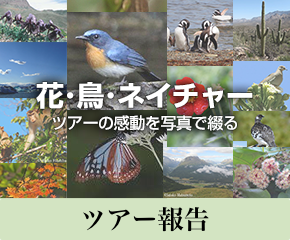【ツアー報告】花々に歌う原生花園の夏鳥と知床の哺乳類たち 2024年6月14日~16日

(写真:マキノセンニュウ 撮影:緑川裕子様)
平成17年7月に世界自然遺産に登録された知床。ここには魅力的な生き物たちが数多く生息していますが、たまたまウトロで大規模な海難事故が発生してしまい、以降、知床行きを躊躇する傾向があることを残念に思っていました。ただやはり我々のような生き物好きには絶対に外せないのが知床です。今回は従来企画してきたシャチとヒグマを観察するクルーズに、新たにオホーツク海沿いにある原生花園の小鳥たちを見る行程を大幅に増やした新企画として発表しました。シャチとヒグマ観察を中心に、夜はシマフクロウ、そして途中に通る知床峠では希少なギンザンマシコ、そしてエゾカンゾウやハマナス、センダイハギ、シシウドなどが咲く原生花園では個性的な夏鳥たちを観察します。クルーズに2度乗船することもあって海況、そして天気予報を注視していましたが、ひとまずクルーズは問題なし、ただ最終日の天気予報があまり芳しくない予報が出ていました。
14日、なかなか梅雨入りしない関東地方はここ数日の最高気温が30℃に迫ろうかといった勢いで、この日も早朝から快晴。最高気温は27℃とのことでした。集合場所の羽田空港周辺も快晴で、週末だったこともあってかなりの混雑で熱気にあふれていました。予定通りご集合が完了したことから、資料の配布、今日の連絡事項をお伝えしてから搭乗口に向かい出発。少々遅れたものの無事到着後は観察機材準備をしてから急いで羅臼町に向いました。そうこうしている間にも船長から「シャチが近くに群れているから早く来い、早く来い」と何度も電話があり、それでなくても焦っているのにさらに気持ちが落ち着かなくなっていました。結果的にはほぼ予定通り15:30には羅臼港に到着して乗船。この日は羅臼町では最新型のクルーザーに乗船して外洋に向いました。天気は曇りながらも空は次第に明るくなってきていて風も弱く、それほど寒さを感じることはありませんでした。うっすらと見える国後島を見ながら進むと周辺をハイイロミズナギドリやウトウ、フルマカモメが飛び、いよいよシャチの大きな背びれとブローが目に入ってきました。船長の話によるとこの日はかなりの群れが集結していてなかなか賑やかだったとのこと。デッキに出ると周囲にはかなりフレンドリーなシャチたちがいて、この日はなぜか背泳ぎのような体勢で泳ぎ回る個体が多く、中にはクルーザーの下を通って右に行ったり左に行ったりする個体もいてかなり盛り上がりました。獰猛なイメージがあるシャチですが、こういったギャップを体感できることもシャチ観察の楽しさだと改めて感じることができました。下船後は一旦、宿に戻ってシマフクロウ観察の準備をしていただき鷲の宿に向かいました。この日の日没は19:00ですが、ほかにも観察している方々がいらっしゃることから、できる限り早めに現地に行って準備を進め、他の観察者の方々に迷惑がかからないようにしています。この日は18:30には現地に到着して少々早めに夕食をいただき、日没時にはすでに準備が完了していました。この日の予定は22:00までの観察のため少々焦っての観察で、しかもシマフクロウの声も全くしていないため心配でしたが、幸いなことに21:30にメスがやってきてかなり積極的に魚を捕って食べる様子が見られ、意外なほど長時間観察することができました。そして22:00近くになって上流に飛び去って行ったことからこのタイミングで観察を終了して宿に戻りました。
15日、この日は前日が遅かったことから早朝のプログラムはなく、07:00から朝食をいただき08:00に出発してヒグマクルーズ乗船場所の相泊港に向いました。早朝に外に出ると風もなく天気は曇ってはいたものの空は比較的明るかったので天気の心配もないように感じました。到着後はトイレに寄ったり、ライフジャケット装着をしたりしながら進め、いよいよ出航。船は実際に昆布漁に使われている船のため、かなり陸地に近い場所を航行しながらひとまず知床半島の先端部に向いました。幸いなことに天気はどんどん良くなってきていて青空も見え始めました。途中、切り立った見事な知床半島の景観に圧倒され、岩礁に群れるウミネコやオオセグロカモメ、ヒメウ、ウミウが見られ、オジロワシの飛翔を見ることもできました。ただ中間地点まで来ると急激に風が強まってきたことから折り返すことにして戻ると、ここでようやく急な斜面を歩く巨大なヒグマに出会うことができ、この個体はそれほど警戒した様子はなく、歩きまわったり向きを変えたりして、時折こちらを見るようなしぐさを見せるなどじっくりと観察させてくれました。また港に戻る直前にも2頭で斜面を歩くヒグマを見ることができ、この2頭はあっという間に森に隠れてしまったものの、驚いたことに下船後に再び斜面を歩く姿を見ることができたのでした。その後は一旦、羅臼町まで戻って昼食の時間としてから移動しました。いつもならば霧や天候不良で探鳥ができないことが多いのですが、この日はほぼ快晴のため駐車場でバスを降りて探鳥してみました。この日はアマツバメが飛び回り、周辺からはアオジのさえずりが聞こえていました。期待していたギンザンマシコは気配がありませんでしたが、あまりに条件が良かったことからそのまま探鳥を続けました。そしてそろそろ諦めようかと思った頃、比較的近くからギンザンマシコもさえずりが聞こえたことから見てみると、ハイマツに止まってさえずる真っ赤なオス個体を見る幸運がありました。その後は道に駅で休憩を挟んでから次のポイントに向いました。ただかなり時間を使ってしまったことから到着したのは予定よりも大幅に遅れた17:20。とりあえずトイレに寄ってから探鳥してみました。周辺では早速ノビタキが飛び回り、間近にオス、メスを見ることができました。その後はソングポストでさえずるノゴマが見られ、ほかにもホオアカ、オオジュリン、シマセンニュウが見られましたが、突然、間近からマキノセンニュウの声がしたことから探してみると、原生花園の囲いに止まってさえずっている姿が見られ、意外なほどじっくりと観察することができました。ここ数年、あまり見かけなくなってしまっていた鳥だけに嬉しい出会いとなりました。
16日、この日はほぼ午前中の探鳥です。幸いなことに天気予報が良いほうに変わって早朝から晴れ。宿の周辺では薄暗いうちからエゾセンニュウがさえずっていました。早朝に宿を出発してまずは朝食を購入し、その後はやや風が強い中、道の駅まで移動して朝食の時間としました。その後はこの日の最初の探鳥地に向い、到着直前にはさっきまでの強風は収まっていて、美しい湿原の風景が目に飛び込んできました。到着してバスを降りると遠くの枯れ木にはツツドリが止まって鳴いていて、2羽のアオバトが飛んでいきました。周辺を眺めるとセンダイハギの黄色い花がきれいで、そこからさまざまな鳥のさえずりが聞こえてきていました。まずは人気のノゴマが見られ、その後はかなりの数のオオジュリンに出会うことができました。そして期待していたツメナガセキレイの声が聞こえたかと思うと、間近に咲いていたシシウドの花に乗って美しい黄色い姿を楽しませてくれました。さらに歩くと湖面にはオカヨシガモの姿があり、遠くの枯れ木にはつがいと思われるオジロワシが止まっていて、頻繁に飛翔する姿を見せてくれました。さらに歩くと元気なコヨシキリがソングポストでさえずり続け、ここでは巣があるようでオオジュリンのつがいがせっせと餌を運んでいました。その後も複数のツメナガセキレイに出会うことができ、想定外に多い個体数には驚かされました。時間がきたことから道を戻ると各所でノゴマ、オオジュリン、ノビタキ、コヨシキリ、シマセンニュウ、そして飛翔するオジロワシに出会うことができ、最後にようやく真っ赤なベニマシコに出会うことができ、ゆっくりと近づきながら観察することができました。その後はこのツアー最後の探鳥地に向いました。天気はさらに良くなっていて風も弱く、探鳥にはもってこいの状況でした。早速、間近に咲いていたエゾカンゾウの花の付近でシマセンニュウがさえずり、遊歩道を歩くと間近にノビタキのつがいが見られました。期待していたベニマシコはそれほど見られませんでしたが真っ赤なオスが枯れ木に止まり、最後はメスもやってきて同じ枯れ木に止まってくれました。
今回、リニューアルした初夏の知床。シャチとヒグマの2大スターはそのままにオホーツク海沿いにある原生花園の小鳥たちも堪能できるようにしてみました。シャチは可愛らしい一面が見られヒグマは知床半島の絶景とともに見ることができました。そして夜はシマフクロウに出会い、翌日は幸運にもギンザンマシコ、そして原生花園ではツメナガセキレイやマキノセンニュウ、そして定番のノゴマやベニマシコ、オオジュリン、シマセンニュウ、ノビタキ、コヨシキリ、ホオアカ、オジロワシなどを楽しむことができました。とにかく今回は海況の良さ、そしてみるみる回復してくれたお天気に助けられた3日間でした。知床羅臼は生き物好きにとってはとにかく素晴らしいところです。海生哺乳類の季節が終わると、あっという間に流氷の季節になります。またぜひ季節を変えて知床羅臼にお出かけください。この度はご参加いただきましてありがとうございました。またご一緒できましたら幸いです。
石田光史